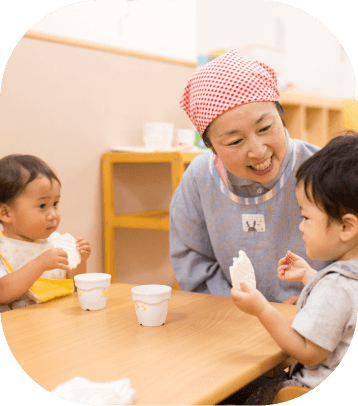はじめに
「3月生まれは保育園入園に不利」という通説は、多くの場合、認可保育園の入園条件と深く関係しています。特に、多くの自治体が定める「生後57日以上」という入園条件が、3月生まれのお子さんの4月入園を難しくする主要因となります。この記事では、その理由から具体的なスケジュール、成功のための戦略まで、より深く掘り下げて解説します。

3月生まれが不利と言われる理由
3月生まれのお子さんが保活において不利と言われる理由は、複数の要因が絡み合っています。
1. 「生後57日ルール」の壁
・認可保育園の原則: ほとんどの認可保育園では、お子さんが「生後57日以上」でなければ入園できません。これは、乳児の健康と安全を確保するための厚生労働省の基準に基づいています。
・3月生まれの現実: 3月生まれのお子さんは、4月1日時点ではまだ生後1ヶ月未満であることがほとんどです。そのため、0歳児クラスの4月入園の基準を満たすことが物理的に不可能となります。
・自治体による特例の確認: ごく稀に、自治体によっては生後57日未満でも、産休明け保育を実施している園や特定の条件で受け入れるケースがありますが、これは非常に限定的です。必ずお住まいの自治体の「保育園入園手引き」や窓口で確認が必要です。
2. 0歳児クラスの4月入園ができないことによる影響
・育休からの復帰時期の調整: 4月入園を前提に育児休業からの復帰を計画している場合、3月生まれのお子さんではこの選択肢がなくなります。結果として、育休期間の延長や、後述の途中入園を検討せざるを得なくなります。
・保活スケジュールの変更: 他の誕生月のお子さんとは異なる保活スケジュールを立てる必要があり、情報収集や計画の立て方がより複雑になります。
3. 1歳児クラスの競争率の高さ
・0歳児からの持ち上がり: 認可保育園では、0歳児クラスに入園したお子さんの多くが、そのまま1歳児クラスに進級(持ち上がり)します。これにより、1歳児クラスの新規募集枠は非常に少なくなります。
・新規募集枠の減少: 例えば、定員10名の0歳児クラスが全て持ち上がると、1歳児クラスでの新規募集は「欠員が出た場合のみ」となります。そのため、1歳児クラスでの入園を狙う場合、激しい競争に直面する可能性が高まります。
・募集人数が少ないことによる倍率の上昇: 少数枠に対して多数の応募が集中するため、結果として倍率が跳ね上がり、希望する園への入園がより困難になります。
年齢別:3月生まれの保活スケジュール
3月生まれのお子さんの保活は、0歳児での途中入園を目指すか、1歳児での4月入園を目指すかで大きくスケジュールが異なります。
0歳児クラスへの途中入園(例:9月入園)
このパターンは、比較的早めの職場復帰を希望する場合に選択されます。
妊娠中(11月〜2月)
・情報収集の本格化: 各自治体のウェブサイト、広報誌、地域の子育て支援センターなどで保育園に関する情報を徹底的に収集。特に「保育園入園手引き(しおり)」は必ず入手し、熟読する
・自治体の「入園手引き」入手: 入園条件、必要書類、選考基準(点数表)、申し込み期間、各園の情報などが網羅されているため、早めに手に入れる。
・見学予約: 産後では見学が難しい場合も多いため、妊娠中に見学できる園をリストアップし、早めに予約を入れる。妊娠中の見学を歓迎する園も多い。
※産後のバタバタを避けるためにも、できる限りの準備をこの時期に行う。夫婦で情報共有し、保活への意識を高める。希望する園の雰囲気や方針、給食の有無、延長保育の状況なども確認する。
出産後(3月)
出生届提出、住民票更新: 出生後速やかに手続きを行い、お子さんの住民票を確定させる。
保育園申込書類準備(先行着手): 多くの自治体で必要となる書類(住民票、健康診断書、就労証明書など)の雛形をダウンロードし、必要事項をリストアップ。特に就労証明書は勤務先に依頼するため時間がかかる。
※産後の体調を考慮し、無理のない範囲で進める。勤務先の担当者と、就労証明書の発行について早めに相談・依頼をしておく。 複数の自治体を検討している場合は、それぞれの自治体の必要書類を確認する。
4月〜6月
保育園見学(継続)、情報収集: 産後体調が落ち着いたら、出産後に見学が可能になった園や、より詳しく確認したい園を訪問。疑問点があれば積極的に質問する。
希望園リストアップ(優先順位付け): 見学結果や通勤経路、園の雰囲気、教育方針などを考慮し、具体的な希望園のリストを作成し、優先順位を決定する。
役所の子育て支援課等で相談: 0歳児の途中入園の可能性や、各園の空き状況、加点制度の詳細、過去の入園実績などを窓口で直接確認する。
※途中入園は空きが出た場合のみとなるため、競争率や過去の実績を確認しておく。 認可外保育園の見学・検討も並行して行うと良い。認可外は申し込み順や見学順で決まることもある。夫婦で改めて話し合い、希望をすり合わせる。
7月
募集情報確認(自治体ウェブサイト、広報誌): 自治体から途中入園の募集情報(欠員募集)が発表される時期。特に注意深くチェックする。
申込み(生後4ヶ月頃): 募集期間内に、必要書類を全て揃えて自治体に申し込みを行う。生後57日以上の条件を満たしていることを確認する。
※募集期間は非常に短い場合があるため、見落とさないように情報源を頻繁に確認する。 必要書類に不備がないか、提出前に何度も確認する。特に就労証明書は発行に時間がかかるため注意。
8月
選考結果通知: 自治体から入園選考結果が通知される。内定が出た場合は、速やかに入園の意思表示を行う。
入園準備(生後5ヶ月頃): 内定が出た園の入園説明会に参加し、入園に必要な物品(布団、着替え、おむつ、連絡帳など)の準備を開始。
※残念ながら内定が出なかった場合でも、諦めずに次月の募集や、認可外保育園の利用を検討する。入園説明会では、園のルールや持ち物、慣れ保育のスケジュールなどを詳しく確認する。
9月
入園(生後6ヶ月頃): 慣れ保育を経て、本格的に登園開始。
※ 慣れ保育は親にとっても子にとっても大きな節目。無理のないスケジュールで進める。 必要であれば、職場復帰の時期と慣れ保育の期間を調整できるよう、事前に勤務先と相談しておく。
1歳児クラスへの4月入園
このパターンは、0歳児での途中入園が難しかった場合や、より長く育児休業を取得したい場合に選択されます。多くの3月生まれのお子さんが目指すことになります。
妊娠中
保育園情報収集(継続)、見学: 0歳児での保活と同様に、妊娠中から情報収集を開始。特に1歳児クラスの定員や、0歳児からの持ち上がり状況についても確認できると良い。
育休計画: 1歳児での入園を目指す場合、育児休業給付金の期間や、職場復帰のタイミングを考慮した育休計画を立てる。育休延長の条件(保育園入園不承諾通知など)も確認しておく。
※育休期間を最大限活用しつつ、保活の準備を進める。 職場復帰の時期と、お子さんの入園時期が合致するか、事前に勤務先と調整しておく。 育休延長が必要になる可能性も視野に入れておく。
出産後(3月)
書類準備(随時): 0歳児保活で作成した書類を参考に、必要書類の洗い出しと準備を開始する。特に就労証明書は、11月~12月の申し込み時期に合わせて最新のものを準備する必要があるため、勤務先との連携を密にする。また、母子手帳や健康診断書など、お子さんに関する書類も確認する。
自治体相談: 生後数ヶ月のうちに、改めて自治体の子育て支援課などを訪問し、1歳児クラスの入園状況や競争率、加点制度の具体的な内容、必要書類の詳細などを確認する。
※産後の落ち着いた時期に、少しずつ書類の準備を進めておく。 自治体の担当者と顔なじみになっておくと、今後の相談もしやすくなる場合がある。 余裕があれば、この時期から認可外保育園の見学も検討し始める。
4月〜10月
保育園見学(継続): 複数園の見学を繰り返し行い、それぞれの園の教育方針、雰囲気、保育士さんの様子、給食内容、園庭の有無、延長保育の可否などを細かくチェックする。
希望順位決定: 見学結果や自宅からの距離、通勤経路、送迎のしやすさなどを総合的に判断し、具体的な希望園のリスト(第一希望から第十希望など)を作成し、優先順位を明確にする。
認可外保育園も検討・見学: 認可保育園の選考に漏れた場合のセーフティネットとして、認可外保育園の見学や仮申し込みも積極的に行う。認可外保育園の中には、申込順や見学順で優先される場合もあるため、早めの行動が吉。
※この時期にどれだけ多くの園を見学し、情報を得られるかが成功の鍵となる。 夫婦で意見を共有し、どの点を重視するかを明確にする。 認可外保育園の中には、認可保育園入園の加点対象となる園もあるため、確認しておく。 複数の候補を持つことで、心理的な負担を軽減できる。
11月〜12月
入園申込み、書類提出: 各自治体が定める申込期間内に、必要書類を全て揃えて自治体に申し込みを行う。この時期は多くの親が申し込むため、窓口が混雑することが予想される。オンライン申請が可能な場合は、そちらも検討する。
就労証明書等の最終確認: 最新の就労状況を反映した就労証明書など、期限のある書類の提出漏れや不備がないか、提出前に何度も確認する。
※締め切りは厳守。書類に不備があると受け付けてもらえない場合があるため、余裕を持って提出する。勤務先に就労証明書の発行を依頼する際は、締め切りに間に合うよう、早めに依頼する。
翌年1月〜2月
選考結果通知: 自治体から入園選考結果が通知される。この時期は期待と不安が入り混じる。
入園準備: 内定が出た園の入園説明会に参加し、入園に必要な物品の準備や、慣れ保育のスケジュールの確認、予防接種の確認などを行う。
※残念ながら内定が出なかった場合は、二次募集や、認可外保育園の利用を本格的に検討する。育休延長の手続きも必要になる。内定が出た場合は、早めに園との連携を取り、スムーズな入園を心がける。
4月
入園(1歳1ヶ月頃): 慣れ保育を経て、本格的に登園開始。
※慣れ保育の期間や進め方は園によって異なるため、事前に確認しておく。 復職後の生活リズムを見据え、入園前から準備を進めておくと良い。
加点制度の活用ポイント
自治体によって加点制度は大きく異なりますが、一般的に以下のような条件で加点が得られる可能性があります。自身の状況に当てはまるものがないか、必ず自治体の担当課に確認しましょう。
●認可外保育園の利用歴: 認可保育園に入園できなかった場合に、自治体の定める基準を満たす認可外保育園(または企業主導型保育事業所など)を利用していると、翌年度の認可保育園申し込み時に加点されることがあります。これは「認可外保育施設利用加点」などと呼ばれ、保活のセーフティネットとしてだけでなく、翌年の認可園入園への足がかりとなります。
●兄弟姉妹が同じ園に在園中: 兄弟姉妹がすでに希望する認可保育園に在園している場合、加点されることがあります。これはきょうだい関係を考慮し、家庭の送迎負担を軽減するための措置です。
●ひとり親世帯: ひとり親世帯は、保育を必要とする度合いが高いと判断され、優先的に加点される傾向にあります。
●保護者の就労状況:
○フルタイム勤務: 長時間勤務であるほど、加点が高くなる傾向があります。
○夜勤・交代勤務: 通常の勤務時間帯以外の勤務がある場合、加点されることがあります。
○通勤時間: 自治体によっては、通勤時間が長いことも加点対象となる場合があります。
○自営業・フリーランス: 勤務形態の証明が難しいため、事前に自治体に確認が必要です。
●病気や介護などの家庭事情: 保護者や同居家族に、疾病や障害、介護が必要な状況がある場合、加点対象となることがあります。診断書などの提出が必要になります。
●その他自治体独自の加点項目:
○育児休業からの復帰: 育児休業明けで職場に復帰する予定の場合に加点されることがあります。
○特定の地域への居住: 人口減少対策などで、特定の地域に居住していると加点されるケースもあります。
○多胎児: 双子などの多胎児の場合、加点されることがあります。
※ 加点制度は自治体ごとに細かく異なり、毎年見直しが行われることもあります。必ずお住まいの自治体の「保育園入園手引き」を確認するか、直接窓口で相談し、最新かつ正確な情報を入手しましょう。
保活成功のコツ
3月生まれのお子さんの保活を成功させるためには、計画性と柔軟な発想、そして情報収集が不可欠です。
1. 妊娠中から保活開始:見学・説明会に積極参加
・フライング気味でOK: 多くの人は出産後に保活を始めますが、3月生まれの場合は特に、妊娠中から情報収集や見学を始めることで、他の親よりも一歩リードできます。
・園の雰囲気把握: 実際に足を運ぶことで、ウェブサイトやパンフレットだけでは分からない園の雰囲気や保育士さんの様子、園児たちの過ごし方などを肌で感じることができます。
・質疑応答の機会: 説明会や見学時には、疑問に思うことを具体的に質問し、不安を解消しましょう。
2. 認可外保育園も併願:見学順・申込順で入園できる園もあり、選択肢を広げられる
・滑り止めとしてだけでなく、加点要素としても: 認可保育園の選考は激戦となるため、認可外保育園を併願することは非常に重要です。認可外の中には、入園申し込み順や見学順で決まる園もあり、比較的入りやすい場合があります。
・質の高い認可外の選択: 認可外保育園の中にも、質の高い保育を提供している園は多数あります。認可外だからと諦めず、ご自身の目で確かめ、お子さんに合った園を選びましょう。
・ 0歳児での慣らし保育の場: 0歳児での途中入園が難しい場合、1歳児での認可園入園までの期間、認可外保育園を利用することで、お子さんが集団生活に慣れる機会を提供できます。
3. 小規模・新設園を狙う:希望者が少ない園は競争率が低く、入りやすい傾向あり
・隠れた優良園を探す: 大規模園や駅近の園は人気が集中しがちですが、小規模園や新設されたばかりの園は、まだ認知度が低く、希望者が少ない場合があります。
・ 新設園のメリット・デメリット: 新設園は設備が新しく、保育士の配置も手厚い傾向がありますが、実績がないため情報が少ないという側面もあります。見学でしっかり確認しましょう。
4. 生活リズムの準備:入園前に早寝早起き、食事・排泄の習慣を整えることで慣れ保育がスムーズに
・園生活への移行をスムーズに: 保育園では、決まった時間にお昼寝、食事、排泄などを行います。入園前からこれらの生活習慣を整えておくことで、お子さんの園生活への適応がよりスムーズになります。
・ 親子のストレス軽減: お子さんが新しい環境に慣れるまでの期間(慣れ保育)は、親子ともにストレスがかかるものです。事前に生活リズムを整えることで、このストレスを軽減できます。
5. 家族以外に預ける練習:一時保育やベビーシッターを活用して、集団生活への慣れを促す
・ 集団生活へのステップ: 慣れ保育前に、一時保育やベビーシッターなどを利用して、一時的にでも家族以外の人に預ける経験をさせておくことは、お子さんが集団生活に慣れるための良い練習になります。
・ 親子の分離不安の軽減: 普段から親以外の人に慣れておくことで、入園時の分離不安を軽減できる場合があります。

まとめ
3月生まれのお子さんの保活は、確かに他の誕生月のお子さんと比較して不利な面があると言えます。しかし、それは「絶対に保育園に入れない」ということではありません。早めの情報収集と計画、そして柔軟な戦略が非常に重要です。
●途中入園の可能性を探る
0歳児での途中入園は競争率が低い傾向にあるため、選択肢の一つとして検討する価値があります。
●認可外保育園を有効活用する
認可外保育園は、認可保育園の選考に漏れた場合のセーフティネットとしてだけでなく、翌年の認可園入園への加点要素となる場合もあります。
●加点制度を徹底的に理解し活用する
自治体ごとの加点制度を把握し、自身がどの項目で加点される可能性があるかを確認し、最大限活用できるよう準備しましょう。
●情報収集と見学を怠らない
園の雰囲気や教育方針、先生方の様子などを自分の目で確認し、納得のいく園選びをすることが、後悔しない保活につながります。
不利な状況だからこそ、焦らず、しかし着実に準備を進めることが、保活成功への道を開きます。諦めずに様々な選択肢を検討し、お子さんにとって最善の保育環境を見つけてあげてください。
ソラストは、東京都内を中心に一都三県で認可保育園、認定保育所などを多数運営しています。ご自宅の近くにあるかもしれません。ソラストの園の認可保育園の数園では43日からお預かりをしている園もあります。そのほか、認定こども園、小規模保育、病児・病後児保育、一時保育も行っています。午睡センサーやセキュリティカメラなど安全のための設備、スマホ連絡帳やおむつサブスクなど利便性、英語教育や体操プログラムなどこだわりの保育内容などがあります。空きは「保育園一覧」から確認可能です。興味があればお問い合わせください。